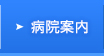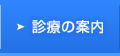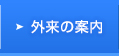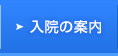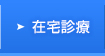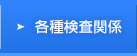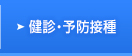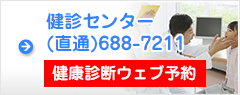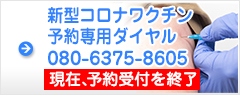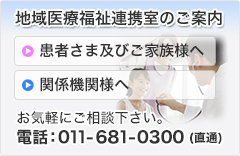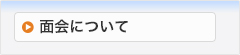2012年9月
平成24年度 インフルエンザワクチン予防接種開始のお知らせ [ お知らせ ]
DATE » 2012.09.28
リハビリ と 『やる気』 [ お知らせ ]
DATE » 2012.09.26

当院リハビリテーション科には理学療法士が3名おります。理学療法とは「粗大運動の回復を目的に物理的刺激、体操などを用いる治療法」です。これは私が学生だった20年以上前に使われていた定義ですが、リハビリテーション医療が対象とする分野が広がってきた今日でも基本的に変更がないと思います。ここで言う「粗大運動」とは寝たところから起き上がって歩くということです。「物理的刺激」とは温熱(あっためたり冷やしたり)、電気、けん引、マッサージなどを指します。「体操」とは筋力・柔軟性・まひ・バランス・体力などを回復させるための運動を意味しています。大雑把に言うと、病気やけがで歩く動作を始めとする様々な動作の障害・困難を上にあげた手段で改善させようとするものです。ですから当然患者さん自身が「運動」をしていただかなくては始まりません。しかし病気やけがをしている人がそうそう運動できるはずもありません。つまり「やる気」が出ないわけです。高齢者であればなおさらです。いわゆる運動の内容よりも運動をすることの誘因が問題となります。健康な人で女性であれば「やせてきれいになる」ことが運動をすることの誘因となりますし、スポーツをされている方でしたら「記録を更新する」「試合に勝つ」ということが動機付けとなります。つまり「馬の目の前にぶら下がっているニンジン」をどう設定するかがカギとなります。運動に対する誘因ができたとして、それを継続するときに必要になるのは効果(結果)です。運動を続けても具体的な効果が見えてこないと、運動のつらさばかりが感じられ挫折してしまうことが多いものです。これを回避するには項目を決めて記録をとり続けることです。体重やウエストのサイズを測ることや、同じ時間内に歩くことのできる距離を時間(日数)の経過に合わせて比較することが、たとえ小さな変化であっても励みになることでしょう。漠然と良くなった・良くならない、痛い・痛くない、ではその時々の気分によって左右されてしまします。できる限り数値で表せるもので変化を確かめることが重要です。極端にいえば、少しくらい痛かったり格好悪かったりしても、その人が出せる能力が高いほうが日常生活を過ごす時に便利です。リハビリ以外のスポーツやダイエットでも同様の対処法が功を奏することがあると思います。お試しください。 <リハビリテーション科 科長 高岡 昌行>
ASV(マスク式陽圧呼吸療法)の学習会 [ 看護部 ]
DATE » 2012.09.19
血管内皮機能を調べる検査として、FMD検査というものがあり、当院でも最近導入されました。
では、血管内皮機能とは、どういうものなのでしょうか。
動脈硬化は、血管内皮機能が低下することから始まります。
血管内皮は、血管の一番内側にある細胞層のことで、血管内皮細胞が弱ると、動脈硬化が速く進行すると言われています。
血管内皮機能は、高血圧、糖尿病、脂質異常、肥満だけでなく、メタボリックシンドロームや、良くない生活習慣(喫煙、運動不足、偏食)でもその機能が低下してしまいますので、日ごろの生活習慣の見直しなどが必要ですね。
文責
- 1